食材のクリエイター特別連載:アグリシステム「未来の子どもたちのために」Vol.2
クリップボードにコピーしました


Article:Hidehiro Ito
アグリシステムは、北海道産小麦によるパン作りを日本中に広めてきた立役者であり、生産者の土づくりのパートナーとして、長年にわたって環境や人間にやさしい農産物を生産、製造、販売、流通させてきた会社。2019年に伊藤英拓さんが2代目代表取締役に就任すると、農業のみならず医療や教育などのあらゆる社会課題の解決にも取り組むなど、活動の幅を広げるようになります。アグリシステムという会社はどんなことを考え、どこへ向かおうとしているのか。伊藤社長が自らの言葉で綴る不定期連載。
刺激を追い求めてきた幼少期
前回の流れからリジェネラティブベーカリーについてお話しする前に、今回は少しだけ、私自身の話をしてみたいと思います。私の生い立ちや、人生の節目の体験が少なからずアグリシステムという会社の経営や在り方にも影響していると思うからです。私の人生の背景には必ず、“人”の物語があります。その物語の一端を、この連載を通じてお伝えできればと思います。
幼少期を思い返すと、人間の本質というのは歳を重ねてもあまり変わらないものだと感じます。自我というものが芽生え始めたのは、小学校4年生のころでした。当時の私は、朝から寝る直前まで、次は何をして遊ぼうかとばかり考えているような子どもでした。おもしろい遊びを考えては、多くの友達を巻き込んで実行に移し、そのわくわくや感動をまわりに共有することに全力を注いでいました。
高校に入ったころから漠然と「卒業したら海外に行こう」と考えるようになりました。比較的穏やかな高校生活でしたが、ファストフード店でアルバイトに励み、3年間の充電期間を経てカナダの大学に進学すると、水を得た魚のように毎日が刺激に満ちていました。大学ではバンド活動にのめり込み、勉強そっちのけで毎日のように歌っていました。ライブで感じた高揚感や一体感は、自分がずっと求めていた感覚に限りなく近いものでした。才能もスキルもまったくなかったけれど、それでも将来はミュージシャンになろうと腹をくくった瞬間、心が不思議とすっと整った感覚を今でも鮮明に覚えています。父親にそのことを告げると、もともと家業であるアグリシステムを継がせるつもりがなかったこともあり、「そうか、がんばれ」と一言だけ。数週間後、エアメールでジョン・レノンの『Imagine』のアルバムが送られてきました。幼少期から父は仕事熱心で、子育てには無関心な人だったので、それが父に対して印象に残っている数少ないエピソードです。その後ミュージシャンは諦め、料理人を目指して大学卒業後にはイタリアに行くなど、行き当たりばったり人生が続きます。
人生を変えたヨーロッパ旅


大学4年の夏、私はヨーロッパに旅に出ました。この旅が今の私の基盤をつくっていると言っても過言ではないかもしれません。「ユーレイルパス」という、ヨーロッパ中の鉄道を自由に乗り降りできるチケットを使って、カナダで出会った友人と二人で、ドイツのフランクフルト空港からなんとなく南を目指すことにしました。最初に降りたのはイタリアのサンタルチアという街でした。水の都として有名なヴェネツィアの玄関口ということもあって街の風景はとても綺麗で、イタリアという国に対する憧れにも近い印象を残してくれました。その日は小さなホテルを見つけて泊まりましたが、これがこの旅で唯一、ベッドで眠れる夜になるとは思いもしませんでした。
次に向かったのはスイスとの国境あたり。宿が見つからず、駅のホームでうっかり眠ってしまい、朝目覚めると、ポケットに入れていた財布からカードと現金が消えていました。旅の2日目で、まさかのスリに遭うなんて。でも、不思議と怒りや悲しみの感情は湧いてきませんでした。むしろ財布の中に5ユーロ札が1枚だけ残されていたことに感動を覚えました。きっと罪悪感か、あるいは旅人へのせめてもの“配慮”だったのでしょう。その5ユーロでカード会社に電話ができ、幸いパスポートとユーレイルパスも無事だったので、まだ旅を続けられると思いました。手元には、カナダから持ち込んだ一本のギターがあったので、私は弾き語りをして日銭を稼ぐようになります。HIPHOPのMCだった相棒がラップを重ねる即興のストリートパフォーマンスで朝から数カ所で演奏し、通りすがりの人々からの投げ銭で、その日の空腹をしのいでいました。そんな日々のなかで、私は一つの真理に出会いました。
「こちらが心を開けば、世界中のどんな人たちも心を開いてくれる」
それは、旅が教えてくれた最初の確信でした。旅に出る前まで「フランス人は冷たい」などと聞いていましたが、一番助けてくれたのは、ほかでもないフランスの人たちでした。パフォーマンスする私たちを面白がってくれ、何かと世話を焼いてくれました。水とパンだけのぎりぎりな生活でしたが、フランスではパンにチーズまでつきました。結局私はヨーロッパ10カ国を回ることができましたが、フランスで味わった人のあたたかさとありがたみを、私は今でも忘れることはありません。
自分たちとは異なる文化、歴史、民族、国家。それらに対して「違和感」や「問題」を感じるとき、その根源は、対象にあるのではなく、自分の中にある「分断の意識」なのではないかと思っています。あらゆる個性や価値観を受け入れ、常識や概念にとらわれずに生きてゆきたい。その感覚を育んだのは、外国で過ごした日々の中にあったと思います。世の中の基準や評価に合わせて生きるのではなく、自分の内側から静かに湧き上がってくる、本質的で普遍的な「何か」を一つひとつ積み重ねていくことが、生きていく上でとても大切なのだと気づかせてもらえました。
キューバで教わった、平和を築く方法


アグリシステムに入社して6年ほど経った2014年、同世代の十勝の農家の友人たちと5人で、有機農業や医療の最先端とされていたキューバに研修視察に行くことになりました。キューバはカリブ海に位置する島国で、1959年にフィデル・カストロとチェ・ゲバラが率いる革命により、当時の独裁政権を打倒し社会主義国家として独立を果たしました。革命後、教育や医療の無償化が進められ、発展途上国としては異例の高い識字率と充実した医療制度を実現。アメリカの長年にわたる経済制裁の中でも、自国のアイデンティティと自立を守り続けてきました。カストロは国家指導者として政治・社会の基盤を築き、ゲバラは理想主義的な革命家として国内外の社会運動に影響を与えました。そんなキューバに私が感じた一番の魅力は、先端を行く農業や医療ではなく、「人」でした。
とにかく国民一人ひとりが幸せそうに生きている。そして子どもから大人まで、みんなが国の歴史を知り、政治を語る。当時、医療や教育はもとより最低限の食は保証されていたから飢えることはありません。職業による給与の差もほとんどありません。だから外資を稼げるタクシーの運転手が裕福だったりします。みんなそれぞれの個性や価値観を楽しんでいて、“就ける仕事”や“稼げる職業”ではなく、自分の一番好きな仕事を選んでいるように感じました。修理だらけでエンジンルームがフランケンシュタインのようなクラシックカーや自転車にバイクのエンジンをつけた自作の乗り物を誇らしげに走らせている。その表情が幸せに溢れていました。市街地にはセントラルパークという公園がところどころにあり、そこで子どもたちと老人が対話しているシーンに何度も出くわしました。「老人は知恵、子どもは未来」なんて素敵な言葉もキューバで教わりました。


この時キューバをアテンドしてくれたのが、日本のJICAで偶然仲良くなったキューバ人のボリスでした。そしてなんと、ボリスの叔父が世界平和運動キューバ支部のプレジデントだということで、急遽彼を訪ねることになりました。ボリスの叔父のシルビオ・プラテオ氏との対話の中で、印象に残っている言葉があります。それは「私たちはいついかなる時でも、どのような国の人とも握手をする準備があります。それがアメリカ大統領だとしても」というもの。キューバは歴史上、イデオロギー対立の文脈の中でアメリカから様々な代償を与えられてきたことを知っていただけに、私は驚き、彼に以前から思っていた質問をぶつけてみた。「世界が平和になるにはどうすればよいですか?」と。彼の答えはこうだった。
「対話を重ねることです。対話で生まれる尊重あるつながりが世界を平和にする」
単にこの文面だけを捉えればありきたりな言葉かもしれません。しかし私にとっては、全体の対話の流れ、実際に見てきたキューバやキューバ人の在り方、その場の空気感、あらゆるものがすべてつながった「言葉」でした。前回お話しした「小麦ヌーヴォー」という取り組みは、この言葉を体現にするために生まれたと言っても過言ではありません。この時のキューバでの体験が、育てる人、つくる人、食べる人がつながり、対話を通じて相互理解を深めることで新しい豊かさのある食文化や流通を創造していく「One Table」というコンセプトにつながっているのです。
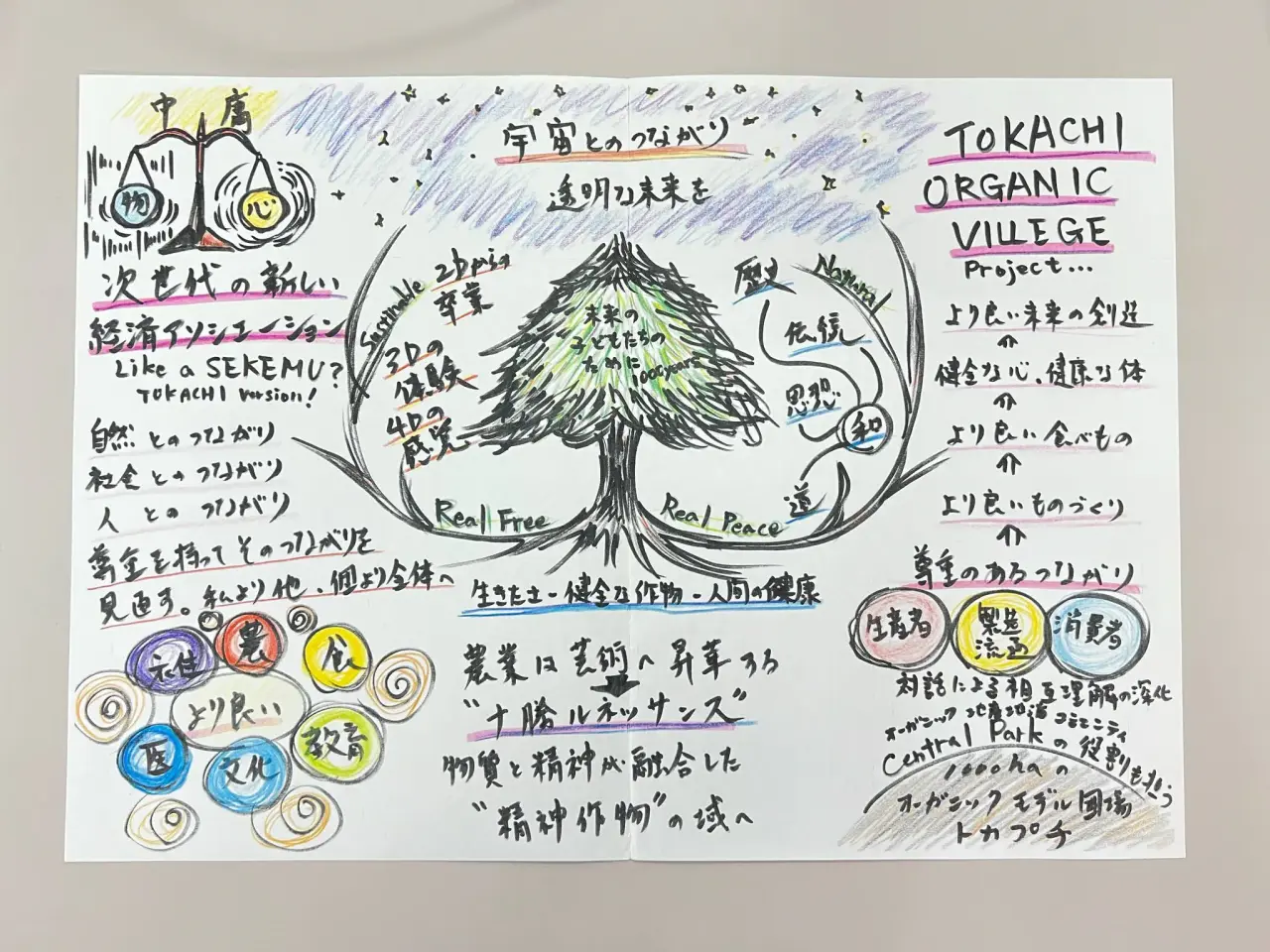
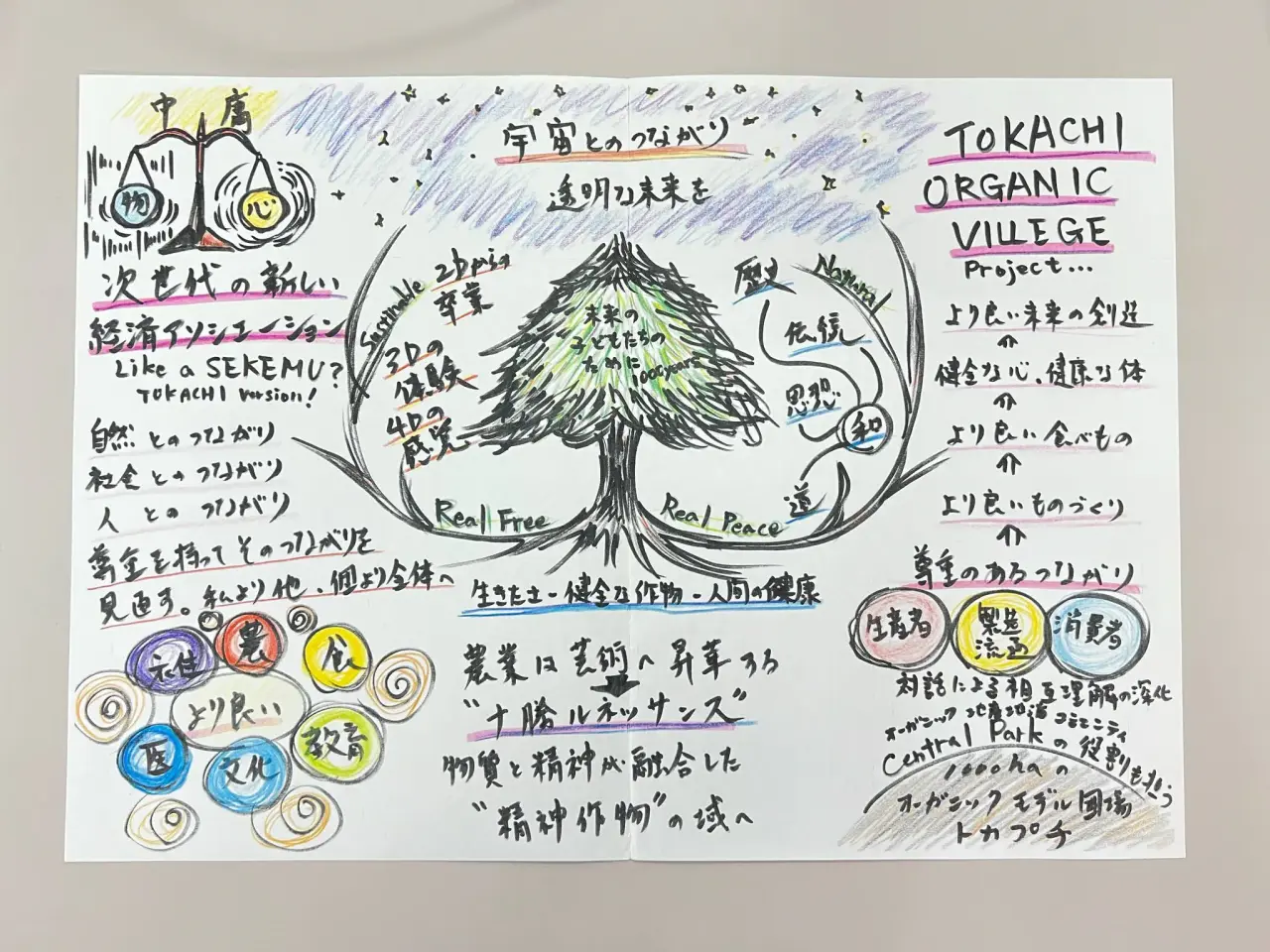
キューバの旅から戻ってすぐに、小麦ヌーヴォーを始めると、始めた当初は目新しさやイベント性にばかり着目されて、「新麦なんて本当においしいのか?」「エイジングしない小麦粉って製品としてはどうなんだ?」と疑問視するような声をよく耳にしました。そのたびに、私たちは新麦の機能性を“売り”に取り組んでいるのではなく、「分断されていた産地と消費地がつながり、対話を通じて相互理解を深めるためにやっているのです」ということを、何十回、何百回と伝えてきました。私にとって経済や事業は“手段”でしかなく、それが目的になることはありません。もちろん事業を継続するためには、経済性も担保しなくてはなりませんが、それは行動した“成果”でしかないのです。おかげさまで、今はなんとかやりたいこと、やるべきことに、収益がついてきてくれている状況です。でも、それがついてこなくなった時は、その事業は役割を終える時だと思っています。
昔、父とこんな話を熱く語ったことがあります。「人が自然との共生に回帰し、農とつながり、あらゆる地域循環が実現した時には、アグリシステムは必要なくなる。それが俺たちのゴールだな」と。きっとそうなった時には、また新たな役割が与えられるのだと思います。


<プロフィール>
伊藤英拓(Hidehiro Ito)
1981年北海道帯広市生まれ。カナダの大学に留学後、アグリシステムに入社。製粉事業をはじめとする新しい試みを続け、2019年から経営を引き継ぐ。小麦、小豆、大豆などをメーカーや専門店に卸す他、大規模バイオダイナミックファームや自然食品店「ナチュラル・ココ」、オーガニック薪窯パン工房「麦の風工房」を運営する。
住所:〒082-0005 北海道河西郡芽室町東芽室基線15番地8
TEL:0155-62-2887
HP : https://www.agrisystem.co.jp/
Instagram:@agrisystem.tokachi